夢枯記012 Stefano Scodanibbio | Voyage That Never Ends
contrabass solo/cd/new albion records/1998
http://www.stefanoscodanibbio.com/
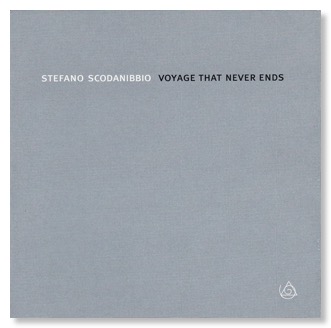
このアルバムは、いつ聴いてもその都度、何らかの新しい旅支度から始まる。今日はこうだった。仕事帰りに近くの何でもリサイクル屋のようなところでたまたま見つけてきた数枚のLP、ホロヴィッツのベートーベンの名演のあと、ジョン・ケージのさやさやっとして繊細にもきこえる弦楽四重奏曲のレコードを聴いて、その流れでこのアルバムを思い出して聴きたくなった。
反復のなかに倍音の豊富な差異がきこえて、音質の差異までもが音色によってさらに差異化され異化されていつのまにかその時空の際をこえだして、変化する時空の連なりをからだで感じながらいまここを出発、遥か遠くに旅に行くことができる驚嘆すべきアルバムだ。音の連打のなかに生じだす音の時空の色の変化が、いろいろな場に僕をつれていく。
この音楽はすべての光を反射するようにしつらえた深い井戸のなかに差し込んでくる光の反射する色をみながら、水滴の過剰な反響を井戸のなかで聴いているかのごとくすすんでいくように感じる。僕は今日、井戸の外から井戸のなかを想像しながらも、井戸のなかで起こっていることのすべてを感じることができる。そんな不思議な夢の中に突入していくのだった。今日は犬山祭の日だったけれど低気圧の大雨、この大雨が地面にたたきつける音も聞こえる。地面が井戸のなかの水だったらきっとたいそうなことになるだろう、深い深い底なしの井戸のなかにしたたる水滴の反響がかえってくるとき、井戸でなにがおこっているのかと想像してみるのだが、想像したとたんに僕は井戸のなかにいて遥か上の小さな空の白光をみている。文字通り底の知れない井戸の底に低音のこだまがどこまでも低く響きわたり、反響し、あるときは水滴が映像写真に写されるスローモーションのように静止しとまって、あるときは水分子が激しく衝突するかのように猛烈なスピードで時が過ぎ去っていくのだ。それはたぶん弦の反応の速さではなく、反応が遅いからこそ得られる低音の音の圧倒的な密度とその残響にもよるのだろうけれど、どうやって弾いているのかというどうしても気になる技術的な憶測はやめておきたい気分。空間的には、場の色の変化の推移に無理がなく、かつ非常に濃厚でコンパクトで凝縮されているし、無駄もなくて無理なく聴ける。でもこういうのは音の現象としての夢だから、いくら書いてもどこか眠りは浅いままだろう。もっと遠くにある旅の向こう側へと、この音楽は僕を誘う。
旅はきっといまここからの脱出でもあって、それは本当には得ることのできない自由を求めてどこまでも続くものだろう。旅とは人生であってそれは音楽でもあるからこのアルバムは人間や音楽そのものを主題としていると考えてもいいのかもしれない。究極的にはその自由とは死なのかもしれないが、死に支えられている時間にさえ生きていれば、時間にはきっとはじまりもおわりもなくて、生きていることもそのうちの一つの現象にすぎないのかもしれない。だから生きて音楽を聴いて、音楽を続けられる。生死、人間という存在までをも、この終わることのない旅の音楽は感じさせてくれる。
祝祭の時間や、今日あるはずだった祭りを夢見る時のように、たとえば子供にきかせて寝付かせるときのおとぎ話は、家族や社会の共同体の硬直しがちな日常的関係性から離脱する時間であるとともに、日常的現実からも非常に遠い空間に僕をつれていってくれる。寝付かせようと読んでいるとこちらの方が物語に夢中になってしまうが、そういうときにこそ知らぬ間に子供は寝ついている。ステファノさんはおとぎ話に集中して、語りかたがうまいというより語りのなかに入り込んでしまった。そういう音楽から僕は生まれてきて、僕はいま、音楽を枕にして眠りだす子供になりつつあるのかもしれない。聴いていたけれどいつの間にか眠ってしまった終わりきらないおとぎ話を聞いていた子供のように、終わらない旅の音が過ぎ去ってしまっても旅はどこかで続いている夢枯れの時間は、音の夢のなかで眠りという永遠の旅に僕をさらに連れ出してゆく。ほんの少しだけ怖くもあるけれど、死ぬほど暖かい眠りという死に僕はつつまれていくのだ。この感触は、ステファノさんも人生という旅の途上で感じていただろうか。音楽のこの不思議な時間は本当に尊いと思う。
それにしてもなぜなのだろう、巨大な音の存在が、聴けば聴くほど、おもえばおもうほど、聴き入るほどに僕のなかに強く生まれて、死の生々しさのようなものが接近してくる。死は怖くないといっているうちはきっと死は怖い、だが死は怖くないものだと想像できるのだ。このアルバムは死に裏打ちされてあるかのように、集中しながらとても落ち着き払って演奏されているように聴こえるけれど、この現代に生きる人間の、生物としての本能的で根源的な何かを響かせながら、音をこえた何かを、聴く度に僕に触発してくる。人間の意識的な創造性だけではきっと為し得ない生物的なアルバムのように感じる。やはりステファノさんの奏でる音が生きものだからだろうか、これを聴くといつも僕はいつの間にか、ステファノさんの音に触れている。

