夢枯記024 Frank Reinecke | Music for Double Bass
contrabass /cd/neos music/2010
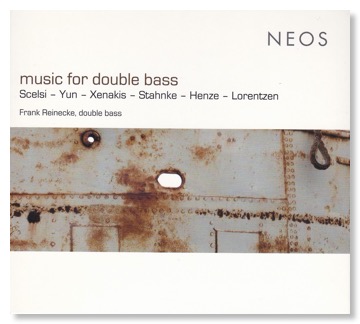
【Yumegareki 024】
This album starts with the work of Giacinto Scelsi and ends quietly with Bent Lorentzen’s for Frank Reinecke in 1993. When I look back on the reverberation, I realize the third difficult piece, “Theraps” by Xenakis, forces me to stare at a certain white space. The sound is like being sprayed to the white background. Its color is nearly transparent with a delicate hue, but the sound comes from afar, from another dimension, and it falls violently nearby. The velocity of this fall tears all the images and imagination from my eyelids. While standing in the white space, I hear the vibration of contrabass, through which I feel my heart stubbed with a sword, but strangely enough I also feel the salvation of my body. The delicate color of the sound has a trait of excessiveness that is represented by the overglaze painting in white repeated since the early age. This music slightly adds colors to the white space, but it eventually disappears in vain. Still the music is strong enough to blur the changes in color over time. It sounds like there is no concept of time and that it is also like creating a strong connection between the past and the future anachronically.
----------------------------------------------------------------------------------------------
この一ヶ月というもの、身の回りで普段は起こりえないであろうことが次々と続いて、やっと日常を取り戻しつつある。聴くのに体力が要るような音楽はなかなか聴く気分になれなかったのだが、そうなってくると逆に日常を連れ去るような音楽を聴きたくなってくる。早朝にうまく起きることができたので、家族の留守なことをいいことにまだ空が薄明かりである時間帯にもかかわらず、大きな音量で聴く。
Giacinto Scelsiからはじまり、Isang Yun、Iannis Xenakis、Manfred Stahnke、Hans Werner Henze、と続いてBent LorentzenのFrankさんのために書かれた「Tiefe」(Depth)という作品で終わる。このなかではScelsiの作品、異なる意味でIsang Yunが僕の好みであったが、それぞれにしっかりとした艶やかな演奏である。「Tiefe」も聴きごたえ十分だった。なかでもXenakisの「Theraps」はいくつかの演奏者のものを聴いたことがあって、以前から気になっていたため、聴く前からどんなふうなのだろうと思っていた。ライナーノーツからかりれば演奏するのはこれまで不可能なほど困難で(traditionally regarded as unplayable)、聴くだけでもハードなこの曲なのだが、今日はなぜか聴くための体力をそれほど奪われることなく聴くことができた。音の透明性がよい意味で確保されているような録音だったからだろうか。
作曲されたものを聴くことは作曲者の試行錯誤の結果として提出された要素が強いとあらかじめ感じるのか、そこに何か音楽という透明の箱があるようにみえてしまう。そこに歴史的解釈が無意識に混入してくるようだ。これをきいて透明なガラスを引っ掻いたときにできる痕跡のように音が聴こえててきてしまうのは、おそらく僕の内側でこの作品を聴くためには音楽の歴史や文脈を知らなければならないというような余計な意識の垢があるからだろうか。そういうことに何となく気がつき始めて、ややもするとコンプレックスにも似ているかもしれないような、だらしのない僕の意識を排除したところで、最後のBent Lorentzenを味わうように聴いてみると、音楽の歴史、音楽の歴史的方向性、言葉にからめとられた音楽の構造的推移のようなものに意識が呪縛されているような場所から、遅ればせながら身体が次第に離れていき、結局は今回も音の確実性のようなものが失われてくる。もはや不確実性の方がこの身体には確かなのだろうか。
アルバムの最後、Frankさんの気合いの入ったLorentzenの演奏が終わった余韻、その静寂のなかで、たとえばXenakisは、コントラバスの音響の独特の深さを、ガラスでできかかってきてしまった箱の壁をいったん可視化し、そこに傷を付け、あるいはガラスの壁を割って壁を通過するための行為として記述したのではなく、そんなことよりも空間を白色で幾度も塗り替え、塗り重ねしていくように試行錯誤した結果なのではないかと、すでに記憶となった数十分前の過去の音を回想していた。実際はどんな感じでつくられたのだろう。
Xenakisの曲には二つの交差する旋律や音色の推移が歪んだ空間をもたらしているようにもきこえるけれど、このコントラバスの音のひびき自体は僕に、「白」を見つめ続けることを促すかのようにある。白はイメージすらもこの眼から引き剥がすようだ。僕は白をみながら聴き続けるしかない。音は色彩に転じようとするのだが、それでも色ははっきりみえてこないのだ。白の基調が空間を覆っている。音自体は無色なのか、あるいは白を着色しないような色の次元、それが音なのだろうか。それとも、白色という状態をずっとみている状態に、未来の人間ならきっとたえられるというのだろうか。
書いていてふと思い起こしたのだけれど、画家の小林裕児さんの個展へ行った時、絵をかくとき光の基準がどうやってつくられるのかがどうしても気になってきて、その辺りを質問させていただいたたとき、確かキャンバスの白地にはじめに十数種類もの白を塗り重ねて地色のようなものをつくると、きいたことがあった。そのあとで原色を大胆に用いた着色がなされてあるが、塗り重ねられた光の基準である白が一部にどこか必ず残されているようだ。白はさらにキャンバスに塗られるのではなく、あらかじめ創造された白があって、それが残されて絵の一部をなしていた。たぶん僕は繰り返し絵を観ていて、その大胆な図柄や絵のテーマよりも、絵の中のキャンバスの白によりひきつけられていったのかもしれない。それは画家のみた光の創造的現成だろう。
未知な色、それも一つのイメージであるといってもよいだろうが、イメージや想像力をどこかさらに凌ぐ要素が身体に残る。しかしそれは原始的な感覚や人間の自然状態というものとも違っている。こういう言い方はXenakisにはあまりあてはまらないのだろうけれど、有が充溢して感じられてきた原始状態たる無を逆方向からみたとき、無から有がみえたその有の残余の色、「ほとんど無色」であるような何か。ある意味で暴力的にも聴こえるこの音楽は、白地に吹き付けられてくるように聴こえてくるこの音は、ほとんど無色であるにもかかわらず、遠くの別な次元から強烈に近くに降ってくる。この降下のスピードによってイメージや想像力すらもがこのまぶたから引き剥がされ、白い空間に立たされながら耳に聴こえてくるコントラバスの響きを通じて、まるで心を剣で突き刺されながら不思議とこの身体が救われるかのようだ。この演奏はカオスのような身体の自然状態が前面に出てこないその透明性が、かえって作品にとってはよかったと感じられたのは、こうしたあたりにあるのだろうか。
医学すらが記号的であるといっても大きな間違いにはならないであろう現代において、音楽はもはやイメージの遊戯や、まして癒しに耽りつづけるための透明なガラスの箱でいつづけることもできない。解明され解釈されようとしてきた過去の歴史の皮膜から脱皮された身体をもって、境界のない開けっぴろげの空間、様々な意味で非常に強い音響のなかへこの身体がその都度落ち込んでいくように、それでも自分を失わずにいまここを旅していくことは、いつものように大切に思える。
コントラバスという弦楽器の音の奥行きその厚さを、空間を煙で埋め尽くしては消えていくような、ガラスの箱のなかのみえない空気を可視化し現代という箱を音響化するための行為のなかに位置づけることはできない。むしろコントラバスの音の響きは、白い空間、それは原始から続く塗り重ねられてきた白でもあり、未知の白でもあるような空間、その白に塗られる微かな白、だからみえないくらい過剰な色としての音、白い何者かをわずかに着色しなおしては儚くも消えるように、前後の白色に変化はあるのか、それともないのかわからないほどに強く、あたかも今という時間がなかったかのように、だからこそ強固に、アナクロニックに過去を未来へとつなげるのである。この作品集は微かな色、そして厚みと深さ(Depth)のある確かな次元を創出していくことへの僕自身の鏡でもあったようだ。

