夢枯記030 Gary Peacock | December Poems
contrabass solo & duo with saxophones/cd/ecm records/1979
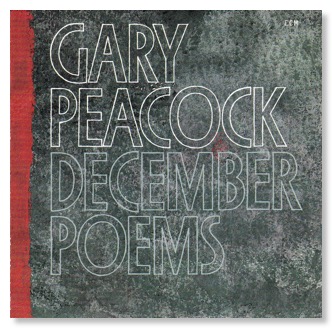
【Yumegareki 030】
Winter moon stands out in sharp contract against the sky, invoking my feeling spontaneously. While the moon maintains a certain distance from the earth, it has a great impact on the earth. Just like that, natural threats are absolutely silent and indifferent to our feelings, but still, they are a distinct mode of nature and strong enough to influence us.
Sounds pierce a freezing winter air, with the bass sound quality and technique crushing my feeling. At the same time, the natural threats are insinuated somewhere behind the sounds. I feel a certain distance from the nature in the sounds as they drift between the nature, which maintains the permanent moon-and-earth relationship, and our natural feeling stimulated by the moon.
The earth’s climate and natural environment are changing. A huge earthquake hit Japan several years ago. I heard that Ginkakuji, Silver Pavilion, built in the late 15 century in Japan, was designed considering the movement of the moon. While listening to the music, I have developed a desire to create silence focusing on the moon, as the natural threats have nonchalantly stroke their fangs into us now more than ever before.
----------------------------------------------------------------------------------------------
先月、夕方ころ東京へ行くとき新幹線からみえる地上すれすれの見事な白色の満月を一瞬みた。地上すれすれは三日月しかみえないと思いこんでいたのでとても意外だった。月の満ち欠けに深い情を抱きつつもその恒久的な動きの冷徹さには時々はっとしてうちのめされる。時空を反転するように太陽を崇め奉った古代人の気持ちを連想した。それからどうしてかいまだにわからないけれど、防空壕で泣く我が子の口を塞いで殺してしまった母親の気持ちを想像しながらだぶらせていた。今年も冬がきたのだと思った。師走に入った。今年ももうすぐ終わる。地球の気象も大きく変わって来たし、近い世間の雰囲気もただならなぬ空気に変わってきてしまった。複雑な心を捨てきれないまま聴いた、言わずと知れたGary Peacock、「December Poems」を手に取った。
これをかけながら僕は多分、もはや音楽を聴く時、楽音やスタイルをほとんど追ってはいない、そういうことに気づく。音に対する演奏家の成熟度とそれを自分自身がどんなふうにどこまで感じることができるかということが、いま、聴くことの基軸にあるのだと思う。それにしてもゲーリー・ピーコックというベーシストは時代を追っていくつかの演奏をきいてみても、通して思うのはどこか不思議な情感のようなものをいつもたたえているということだ。けれど情感というのは正確な表現ではないかもしれない。むしろ情のなさが一つの自然発生的な情をもたらしているといったほうがしっくりくるだろうか。そのあたりが表現しずらいようなベーシストで、僕にとって気になる存在だ。
このアルバムを聴いていると、1979年、ECM盤で、この音質と表現形式からすると、ややもするとある種の甘い情感や雰囲気をひたひたと謳歌している音楽にもきこえなくはない。こうした類いの音楽はきっと好き嫌いが大きくわかれるだろう。しかしそれだけで片付けられないものも聴こえてくる。張りつめた冬の寒さを破る音の息、そして気の冷たさを揺動させながら次第に温めていくような低音の気流が、ジャズというテクニックやスタイルを超えて、その底辺にはあるように聴こえる。
空気が冷たくなると世界のなにもかもが止まるように感じる。日本の師走の世間、あの活気ある忙しさとも無関係な、自然という場所がある。自然はいかにも厳しい、そんな表現さえ全く当てはまらないような自然の脅威というものが現にあった。人間は自然から生まれたが、同時に人間は自然から放り投げられていて、自然にあれこれ投影して甘える事は人間の勝手な情事にすぎない。たとえば写真の世界のように、心というものがなかったら人間に世界はどう見えるか、どう聴こえるだろうか、そんなこともちょっと想像した。2曲目にさしかかりJan Garbarekのサックスが絡んでくると音やその奏でる旋律の雰囲気に浸るどころか、なぜか世界がとてもむなしくさえなったけれど、心が空っぽになったのではなく、どちらかといえば空しい心情が芽生えたような感じが近いだろうか。このあたりの微妙さが何とも言えない不思議な感じで、禅というほどではないが、ゲーリーさんにとってある探求の過程にある、そんな感じを抱く。
人間というものは誰しもその性からか情緒的な音楽を必要としたり、音楽に何らかの情を勝手に抱こうとするのだろうけれど、時に音楽が自然とまさに一体化するようなことがあれば、音楽自体がある種の脅威的で、ときに暴力的な自然を呈したりもする。音の脅威がそういう自然過程から生じるものであるならば、それは人間の過度な感情や支配欲、あるいは正義や主義主張によってさかなでされるように生まれた暴力的な音とは全く別種の、世界のなかに自分自身がいるということ、存在するということの大いなる一つの証であり、今の時代、慰めとさえなるかもしれない。脅威とは一つの自然の明らかなる有り様であり、それは静寂と表裏一体だろう。そのような脅威としての音の外側に音のない静寂がどこからともなくきこえてくる音楽、いわば情なき情の聴こえる音楽。この録音にはそういう気配がどこかに漂っているようだ。
自然の脅威がある種の静寂性を帯びる。そのような音を出すこと、自然の驚異や脅威を音にすること、あるいは自然が音そのものとなることは、心を空にしながら、なおかつ人間でなくてはならないから並大抵のことではできないだろう。だが人間はある意味すでに、そういう自然に図らずも突入してきてしまったといっても間違いにはならないのかもしれない。だがそれは、たとえば厳しい坐禅を通じて得られる境地などではなくて、人間の進歩ならぬ退歩によって、きっと古代とは違う形で、自然の脅威が人間に再び姿を現し、人間の心の暗部をふたたび強く照らし始めたということでしかない。そして音楽はもっぱら、驚異的な自然と対峙したり交感したりするための成熟した文化どころか、自然の脅威からのがれるための自己中心的な娯楽になり果ててきているようにみえる。その裏で自然は人間とは無関係に牙を剥く。当たり前だけれど、人間の情や思考というものを自然は都合良く汲んでくれたりはしない。非情な自然から紡ぎだされてくる音と、情が自然を鏡としながら出される音、そのどちらとも受け取れるのが、このアルバムでのゲーリーさんのベースの音の魅力かもしれない。
この音楽は寒くて凍てついた空気を、甘いベースの音質とテクニックが情を裂き、情をかみ、情をくだきながら通っていくこと、それと同時、裏腹に、自然なる脅威のようなものが、オブラートに包まれながらもどこか遠くに近くに暗示されているかのように聴こえてくる。情であるようで、情なき情の音楽、そういう絶妙なバランスの上に成立している音楽は意外と聴いたことがなかったように思う。こうした感想は僕の勝手な憶測でしかないとも思ったが、何度か、それもオーディオをかえて音質を変えて聴きなおしてみても、単に情から生まれた音の動きでは決してないとわかる。
静寂という凍てつく自然の空気の変化にやってきた「December」、日本とも違う北半球の冬の大気に包まれた音楽であるだろうが、ここに録音されているのはやはり、ゲーリー・ピーコックという一人のベーシストの踏み歩んで作られてきた音の道の体現であり、身体を包む膜を通じて静かに奏でられる音の成熟そのものであるにちがいない。そうであるからこそ冷たい自然の空気の気配が音にはっきり浮き彫りにされていた。その空気に晒され照らしだされた奏者自身の内部と、外的な自然の冷たい空気自体のあいだに音が漂い、どこかむなしく消えていく。
一つの自然への対峙の仕方がみえてきて、自然と人間との近くて遠い身体的な距離感が聴こえたように思う。旋律や音質によって醸し出される「冬の詩」としての音楽性ではなく、その自然への距離感が詩的で、このアルバムは、私たちは自然と一緒に、あるいは自然から離れてどこへ向かうべきか、その距離のとりかた、そのあり方を問うている音の詩であるように今の僕には聴こえてきた。
人間はいまや月をも強いもの早いもの勝ちで所有しようとし、所有した気にさえなっている。それに間もなく誕生するだろう人工生命はやがて人間自身をも凌駕し駆逐するかもしれない。それでもやはり自然は容赦ないだろうし、月は地球の周りを一定の距離を保ちながら回っているだろう。室町時代、銀閣寺の庭の設計は、月の運動との関係が密接にあるときいた。月と地球の関係が恒久的であるような自然と、月をみて情を抱くことのあいだを漂う音の詩。だがいま、前者の自然である月を凝視した音が出せればと願う。

