夢枯記027 Adam Linson | cut and continuum
contrabass solo, processing, sampling/cd/psi records/2006
http://www.percent-s.com/
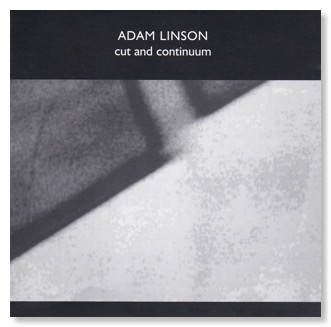
【Yumegareki 027】
As a whole, I perceived the Human-Computer interaction. It is well designed in expressing the concept of time by reconfirming it philosophically through music. Its title and the names of some pieces are the quotes from Cinema II by Gilles Deleuze. It places time through contrabass at the junction between philosophical consideration and electronics music. This is a bold challenge to jump to the new dimension where time and image are exchanged. Interoperation of these sound effects creates a sterical image of time.
On the other hand, the embodiment of the future through a critical reflection of the modern times may be shielded by both the mental processing of the sounds and the excessive sound effects. Sound opens up a mistrial temporal experience that goes beyond the interpretation with words, demonstrating the acoustic vertical variation of the intricate nature projected directly from the body of the performer. But his performance seems to limit these variations and retreat from such a direct experience.
This approach of recompiling sonic pieces of the body through computer, a virtual brain, demonstrates the issues related to the alienation of our body in modern days. This album dares to offer a glimpse of this fundamental dimension of our animalistic survival instinct by posing a question of how our body can survive in this world. Although Deleuze committed suicide, he must have tried to recover a sense of trust in this unbearable world through philosophical body. I want to label this album as a token of such a desperate act.
----------------------------------------------------------------------------------------------
全体の印象としてはコントラバスのエレクトリックな音と、エレクトロニクスそのものとの対話のような音楽で、Human-Computer interactionという形が聴き取れる。いつもとは違う感じでスピーカーと妙に相性のよい音がする。エレクトロニックの音はいくら爆音でなってノイズに満ちているような感じがしても、どこか澄んでいてきれいな音にきこえるのはなぜだろうか。すでに僕の耳はさまざまな電気音に毒されているとはいえ、それでも、それが深い身体的次元から遠のいたサンプリングの電気的変換であり、どんなに凝って制作され工夫されていたとしても、結果としてはいつも聴いているスピーカーの膜面の効果音としての側面が強調されるにすぎないと短絡的に認識してしまうや否や、僕のなかで音楽を聴く欲求が減退していくのはどうしたらよいことか。
アンプで拾い、コンピュータのプロセスを通じた音は無限の音量を持ちうるが、音質のバラエティは著しく制限されるように聴こえる。ある意味において音はのっぺらぼうで、どんな細かくダイナミックな音の起伏をつけても僕のなかでほとんど身体的な摩擦が生じないのである。僕にとっては、極端に云えば音がそこにあってないようなものだ。もっと極端なことを言えば、できれば奏者の弾いている姿をみて音を遮断しながら想像する方が、僕にとって、無としての音楽がかえって聴こえてくるのではないだろうか。自然のゆらぎの音とはやはり大きくちがって、頭脳的な音がする。もともとあった自然の振動、ゆらぎが過度に抑制されたり、あるいは正弦カーブが直線的に合成され増幅されたりしているのが不自然だからだろうか。出せる音の範囲や音量に制限のある楽器の生音が、音色や音質や倍音のありかたが無限であるのとは対照的だ。どこか平均的な音がする。
こうした不自然な音質の均質性によって、ある音の領域の欠落した感じのなかに入り込んで、このアルバムを聴くことができるようになるまでにはかなりの時間がかかった。だが、しっくりくるような摩擦のないままに、この音の受け入れ態勢を身体が模索し、そこを通過していって、その欠落された音の中にいったん入ってしまえば、演奏者の表現の道筋をそれなりに追っていけるようにもなるようだ。そういう意味では非常に聴きやすい音楽で助けられたともいえる。自分の拘泥している部分から離脱して何とか音の空間に突入してみると、アルバムの意図もはっきりしてくるようだ。
この音楽では時間という音楽における重要な要素が、実に空間的に見えてくる。音楽の時間のなかにそのまま入り込むと、音が聴こえる時間そのものはむしろ見えなくなるというのとは逆に、そこに時間が何かの図形の変化としてあるように聴こえる。これも電気、コンピュータの音空間の一つの特徴なのかもしれない。これはこれで音質や音とは何かという問題は考えられているだろうし、非常に精密に様々な即興的断片が織り交ぜられて作り上げられている気がするけれど、それらのことはあたかも二の次で、音の効果と効果の相乗作用が屹立させてくるような次元に、時間が立体的に見えてくるという感じがいいのだろうか。時間が第4の次元だとすれば、その次元に身体が自然と入り込みながら時間的宇宙を実感していくのではなく、作り方は込み入っているのに、むしろ時間という次元をわかりやすく第3の次元にひきずりおろしているように僕には聴こえてきた。これは短絡的に過ぎない僕の思考の欠落、あるいは僕の聴き方が哲学的な新しい時間、「新しい音の次元」についていけないだけなのだろうか、どちらかは確信的にはわからないが、「知」がなければ聴けない音楽ということならばやはりどこか疑問だし、気安くはこの音質を受け入れることはができないのが僕の現状だということだろう。
ジル・ドゥルーズの「シネマ2」という分厚い著書からの時間とイメージについての章「The Time-Image」からタイトル「cut and continuum(切断と連続)」が引用されているようで、第一曲目の題名も「peaks of present and sheets of past」、おそらく挿入的な第二曲目を経て、第三曲目も一曲目に続く「slivers of crystal-images」となっていて、同書のキーワードのようだ。内ジャケットにも同じ章から引用された文章がある。テーマとしての時間がアルバムの根幹にあるのだろう。音楽そのものが摩訶不思議な時間的体験をひらきながら導くというのではなく、音楽によって時間を哲学的に再認識しながら表現しているように聴こえる。音楽による時間の定義、あるいは時間の表現としてのエレクトリック音楽はいまだに僕の耳と身体には響かなかったが、哲学的な考察とエレクトロニクス音楽の接点に、コントラバスを通じた時間を置くということは、コントラバスの新しい次元へのチャレンジとしてもあるのだろうし、コントラバスの音色の一つの変化となって音や音楽の変換になりうるのかもしれない。あまり聴いたことはないが、この類の音楽の作品としての出来映えもおそらく非常に高いにちがいない。
しかし音楽とはそれ自体で時間を自然に顕現させるもので、言葉の定義をこえた時間的な何かを音連れさせるものという観点からすると、いわばやや低いであろう別な次元でみれば、実はこの方法はむしろ、人間の技術的進歩に思考がのっかっていくことによって逆に音楽そのものから退行していくこととしてとらえざるをえないようにも思えてくる。「シネマ2」のある部分においてドゥルーズの語っているような、現在の過去と未来への時間の分裂性、二方向性やそれらのイメージの「結晶された時間」に対する音の連鎖は非常に工夫されてあるし、この退行は人間の現在と破滅への未来そのものでもあり現在を象徴しているという点では、素朴には肯定的にとらえるべき方法かもしれない。しかし不穏な未来へとそのまま突入する時代のまえに立ち、待ったをかけ、この時代を批判的に聴きながら未来を担うための身体性が、演奏者のどこかに聴き取れるにもかかわらず、むしろこの批判的身体性が絶大なる音響効果によって遠く隠され、打ち消されているような気がしてくる。逆にそこに現代的な身体性も感じられてくる。
身体の断片を脳で再編集するという問題、またそれがしきれるかどうかという問題を暗に投げかけているような気がして、脳について脳が考えるという矛盾に脳を含めた身体がはまっていくような不自然な居心地の悪さ、感触の悪さがつきまとい、臓器移植の諸問題とこの感覚は僕のなかで感触が似ている。エレクトリックス、コンピュータを駆使した音楽がこれからどこへ向かうかという未来的で哲学的な意義よりも、Adamさんのこの音楽は、ついにパンドラのふたを開けて翻弄されながら自滅していく人間をどのように受け入れつつも生き延びるかという、人間の生存の問題に、むしろ無意識的に直面しているのかもしれない。僕も「差異と反復」という概念にとても影響を受けた一人だが、自殺したドゥルーズともこの問題はかぶってくるような気がする。とすれば、やはりもとを正せば人間の動物的生存本能という非常にシリアスな問題が、このアルバムの身体性を支えているのではないだろうか。
エレクトロニクスやコンピュータミュージックは、いまの僕の耳や聴く身体に変化することを強いてくるけれど、こちらがそれに合わせるように身体ごと変化しなければならないというふうにあえてこの音楽を受け入れず、その横道にそれて空間に屹立してくる時間をみながら、聴こえてはこない複雑な倍音と自然のノイズをこの時間の外に思い描くとき、人間の失ってきたものへの痛いほどの郷愁が襲ってくる。もはやノスタルジアでさえもあるのだろうが、失われていくだろうもの、でもまだ現存するものを写真に撮ったり、古層にある変わらないものを音に追い求めていくことが自分の道であるように今日もどこかで感じていた。そして僕がそのように自分の道を感じたように、Adamさんもまた自分の道を愛し、信じているように感じられた。パンドラの蓋、その一つを閉める行為への道筋(ドゥルーズもこの耐え難い世界への信頼をとりもどそうと試みたという)と、このアルバムを個人的にはとらえたい。
時間とは過去、未来、現在という時系列ではなく、そのたびに何かが生まれ出づる源泉のようなものだとある哲学者がいっていた。サケの産卵のように、水の一分子であった自分がその源泉に命がけで近づき、死に絶えながらも一つの河の流れを得て小川がつくられ、陸地を蛇行し下りながら海にもどってくるための自己愛は、まだある未来においても尊いにちがいない。人間にとってはそれは困難な道だが、道半ばにしておわるにしてもその形は無限にあって、無限の場所で繰り返されていくだろう。一つの夢枯記を書くことによって、今日も一つのコントラバスの音楽の時間を生きたと、思うことができたようだ。

